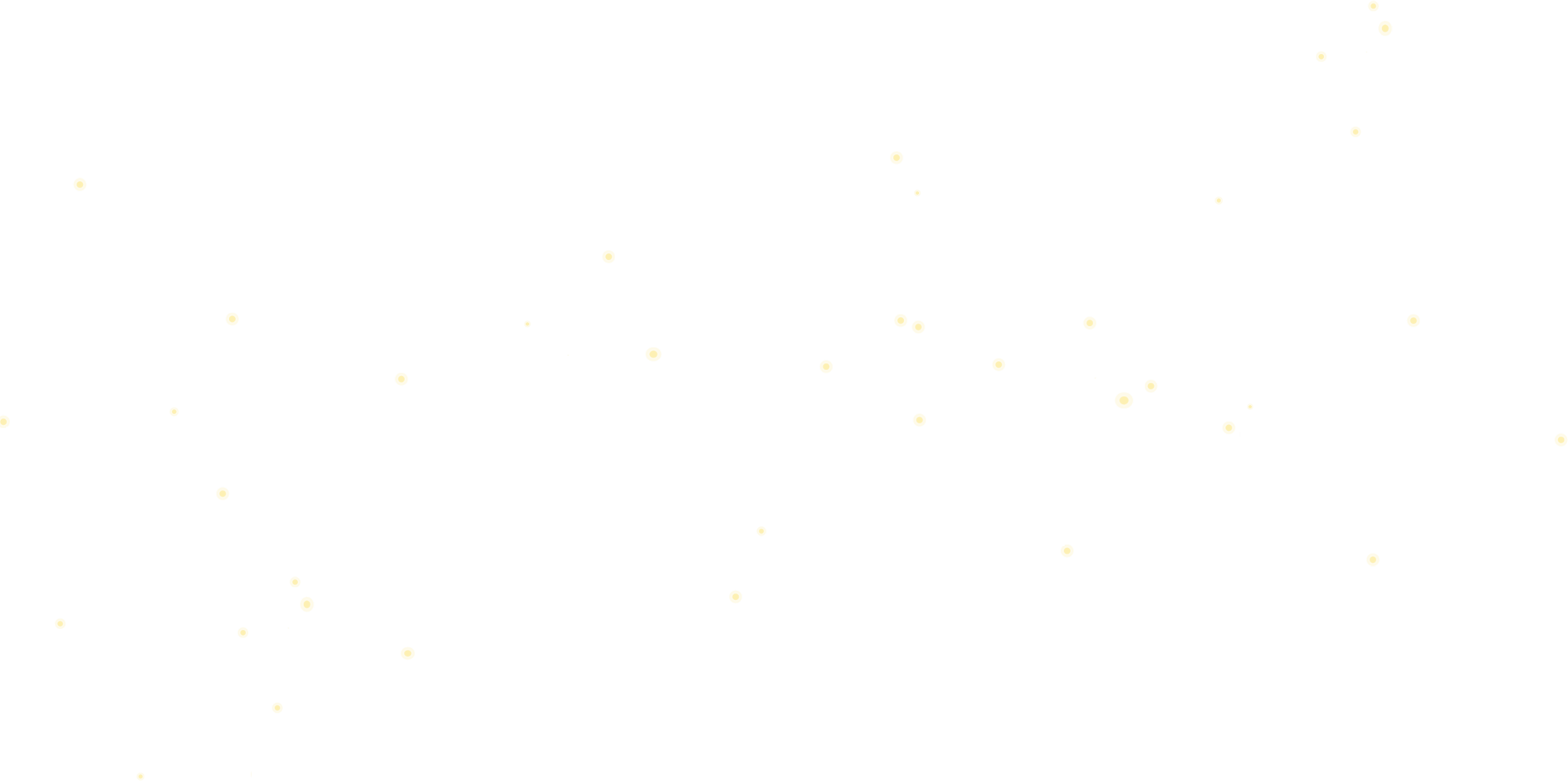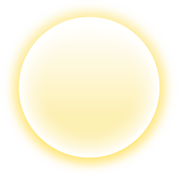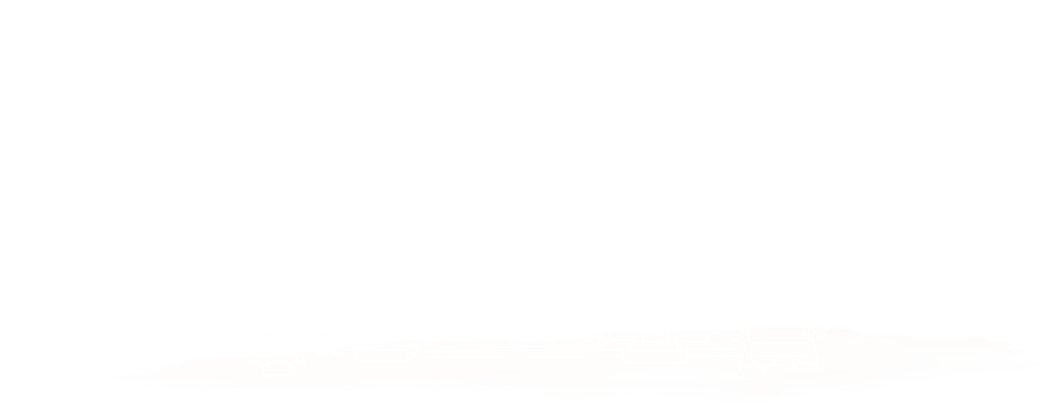終戦80年 溝旗神社に残る戦争の爪痕
ーよの木とおしゃごじ二福ー
境内には、かつて「よの木」と呼ばれた大樹が立っていました。
「よの木」とは「世」「代」の境を守る木の意ともいわれ、樹齢七百年、幹回り二十五尺、枝は境内を覆い尽くすほどの巨木で、古くから狐の集まる霊木として語られてきました。狐は稲荷大神の御使いであり、その集う姿は神霊の依り代として崇められてきました。 木の根元には「おしゃごじ二福(大黒天・恵比寿)」が祀られていました。
「しゃごじ」とは「塞ぎの神・来るなの神」の意で、村の入り口や境に二福を祀り、人々を外敵や災いから護る古い風習を指します。よの木と二福が共に鎮まることで、境内全体、氏子域を護る結界として敬われてきたのです。 昭和二十年、岐阜空襲の夜、焼夷弾の炎は社殿や木々を焼き尽くしましたが、記録にはこう残されています。
「木の内部に引火するも、外側は燃えず、そのため手水舎や神楽殿、鳥居付近を守り抜き、厄を除けた」
やがて丑満の刻、大音響とともに大地に横たわり、その大任を終えました。 しかし不思議なことに、その後同じ場所から新しい木が芽吹き、いまも榎(えのき)として境内に生い茂っています。根元には変わらず二福がお祀りされ、かつてのよの木の記憶を受け継いでいます。 一つの境内に、我々の生活で重要な衣食住や豊穣を願う神々である 稲荷大神、大黒天、恵比寿が一同に集う杜。そして、厄災を塞ぐ神々とご神木の杜でもあります。
その姿は、戦火を越えた祈りの象徴として、今も参拝者を見守っています。